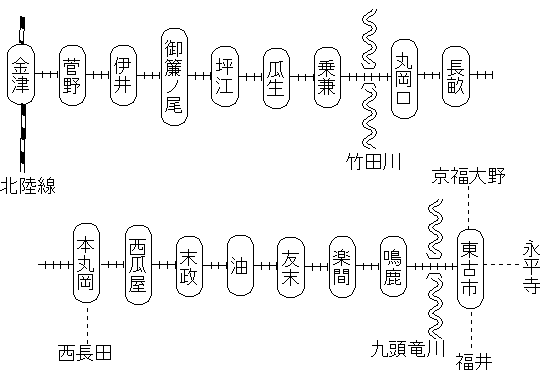
京福電鉄永平寺線 金津-東古市間 廃線跡巡り
昭和44(1969)年9月17日に廃止された京福電鉄永平寺線金津-東古市間の現在の様子をお伝えします。
京福永平寺線は、曹洞宗の大本山永平寺への参詣客輸送を目的に設立された永平寺鉄道が、大正14(1925)年9月16日に永平寺(後の東古市)〜永平寺門前間を電気運転で開業したのをルーツとする。
さらに省線への連絡を目指し昭和4(1929)年8月4日に金津(現・芦原温泉)〜新丸岡間、同年12月10日に新丸岡〜永平寺口間を開業し24.6kmの全線がつながった。
丸岡鉄道とともに戦時統制で、昭和19(1944)年12月1日に京福電鉄に吸収合併させられた。
戦後の経済成長期にいたり道路網の整備と引き替えに旅客貨物とも減少し、金津〜東古市間が昭和44年限りで廃止された。
東古市〜永平寺間については別項に譲る。
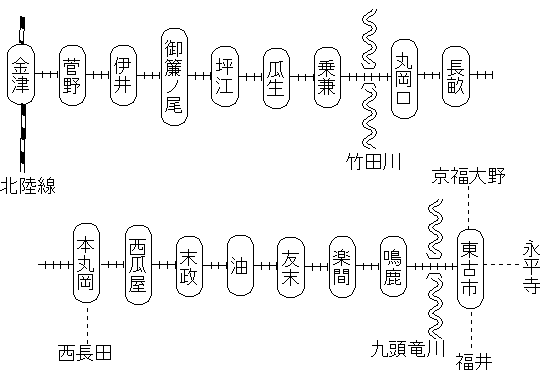
 |
東古市駅 (現在のえちぜん鉄道永平寺口駅) 画面右の6101型は上り福井行き、5001型は下り勝山行き 永平寺線は東古市で越前本線とX字状に平面交差し、画面手前を左に折れて金津方向、画面奥を右に進んで永平寺方向であった |
 |
永平寺鉄道が建てた変電所 福井県内最古とも言われるレンガ造り |
 |
東古市駅 ホームがそのまま残る |
 |
国道364号線の踏切に埋められたレールが残る 右は越前本線 |
 |
越前本線と分かれて九頭竜川方向へカーブする築堤 この先九頭竜川まで痕跡は何もない |
 |
鳴鹿橋梁を受ける右岸側の橋台と築堤 手前の田んぼも昔は川(用水路)だった |
 |
鳴鹿側の築堤上から九頭竜川を望む |
 |
築堤の根元にあった標柱 |
 |
この水路は廃線当時からのものとは思えないが、記念に残したのであろうか それとも今でも土地境界の役をなしている? |
 |
鳴鹿駅跡 片面ホームの無人駅だった 発車してすぐ築堤を駆け上るのは電力消費が大きく、駅を東二ツ屋に移動した時代もあったという |
 |
鳴鹿〜楽間間の線路敷きは農道として残る 画面これより手前は丸岡市街地まで2車線道路となった |
 |
末政駅跡 線路敷きは歩道付きの幹線道路と化した 画面中央の建物は廃線当時からあった 貨物引込線を備え農作物の収穫期には大忙しであったという |
 |
西瓜屋駅跡 ホームと線路敷きがそのまま残る |
 |
ホームの増設部分は古レールで作られている |
 |
西瓜屋を出て本丸岡への線路敷きは道路に転用された(画面中央) |
 |
本丸岡駅跡 丸岡線との乗換駅でもあり広大な敷地はバスターミナルとして利用されている 画面奥が東古市、手前が金津方向 |
 |
本丸岡〜丸岡口間の約0.6kmには市街地ながら不思議にも数々の遺構が残る |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
丸岡口〜長畝間の築堤 |
 |
ここにも標柱があった |
 |
長畝駅跡 民家の裏にホームが残る |
 |
長畝〜乗兼間の竹田川橋梁 右岸(乗兼)側 |
 |
竹田川橋梁 左岸(長畝)側 |
 |
乗兼駅から移設されたバス停 同じような古レール製の待合室は友末や諏訪間にもあった |
 |
乗兼集落内の橋台 線路敷きは民家の庭になっている |
 |
乗兼集落南端にあった標柱 |
 |
乗兼〜瓜生〜坪江間は農道として残る 画面奥が金津方向 すぐ脇の国道8号は車が絶えない |
 |
瓜生付近 画面手前が金津方向 |
 |
金津駅進入路が遊歩道になって残る 廃線後も菅野までは化学工場への専用線としてしばらく残っていた。 |
 |
|
 |
金津駅を出るとすぐ左へ大きくカーブして丸岡へ向かった |
 |
金津駅跡 京福側にに出入り口なく、京福側からの住民も国鉄側に迂回させられたという |
 |
金津車庫付近 画面右の大きな木は往時を知っているのであろうか |